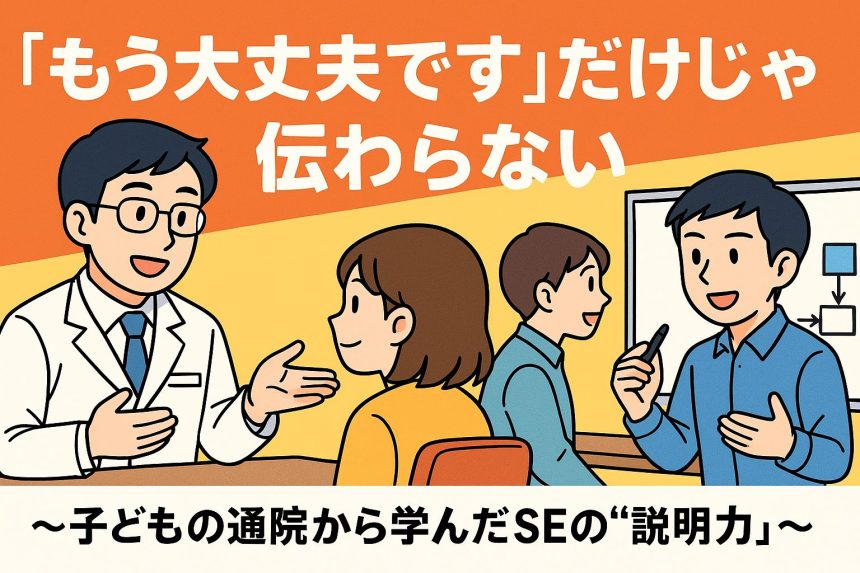はじめに
※本記事の一部コンテンツ(文章・画像)はAIの支援を受けて作成しています。
子どもの通院での出来事から、「説明されることの安心感」について、改めて深く考えさせられた。これはシステムエンジニアという仕事においても、決して無関係ではない。
小児科と耳鼻科、それぞれで診てもらった子どもたち。どちらの先生も技術的にはしっかりしているのだろう。しかし、受けた印象はまるで違った。そしてその差は、「説明があったかどうか」に尽きる。
これは、普段のSEとしての私たちのふるまいにも重なる話だった。そんな気づきを共有したい。
病院での体験:安心と不安の分かれ道
小児科:説明から生まれる安心感
長男を連れて、かかりつけの小児科へ。湿疹がひどくなったので、以前もらった薬を再度処方してもらう目的だった。
診察では、症状について細かく確認してくれた。
- どこが一番ひどいか
- 家での様子はどうか
- 前回の薬の効き方
「薬は切らさないように」とのアドバイスに加え、子どもに対しても「痒かったの?」「掻いちゃだめだよ」と優しい声がけがあった。
些細な言葉かもしれないが、この丁寧な確認と説明が「ちゃんと診てもらえた」「ちゃんと見立ててくれた」という安心感を与えてくれた。
耳鼻科:説明がないことの不安感
その後、長女を耳鼻科へ。こちらは評判があまり良くないと聞いていたが、過去にも同じ症状で診てもらっていたため、取り急ぎ連れて行った。
診察はスムーズに進んだが、会話らしい会話がほとんどない。
- 自分から話しかけないと説明が始まらない
- 終わりの言葉は「もう大丈夫です」だけ
何が原因だったのか、本当に大丈夫なのか、どこまで治療したのか。こちらが知りたかった情報は何も得られず、結局「自分で察する」しかなかった。
エンジニアにとっての“説明”とは
ふと、医師の立場をSEに置き換えてみた。
我々が顧客や上司、同僚に向けて仕事の進捗やトラブルの報告をするとき、同じようなことが起きていないだろうか。
「もう直りました」「対応しました」
たったこれだけの報告で、相手は納得してくれるだろうか。
エンジニアとして働くうえでの“説明力”の話
説明力とは、決して難しい専門用語を並べることではない。
- どんな問題があったのか
- どこまで確認したのか
- どう対応したのか
- 今後の注意点はあるのか
これらを“相手の目線で”説明できるかがカギだ。
小児科の先生はそれを自然にやっていた。耳鼻科の先生は、それを怠っていた。
技術力があることと、信頼されることは別物だ。
自分も昔は“説明不足なエンジニア”だった
若いころの自分も、似たようなことをしていた。
- 「説明しなくても分かるでしょ」
- 「技術を知らない相手が悪い」
そんなふうに考えていた。
でも今ならわかる。
説明とは、「信頼されるための技術」でもあるのだと。
おわりに
日々の業務に追われていると、「もう大丈夫です」だけで済ませてしまいがちになる。
でも、それでは相手の不安は拭えない。
今日の病院の一件で、「説明することの力」を改めて実感した。
顧客や同僚に安心してもらえるSEでありたい。
たとえ忙しくても、ほんのひと言でもいい。
「どこを見て、どう対応したか」
それを伝えるだけで、安心感と信頼感は大きく変わるはずだ。