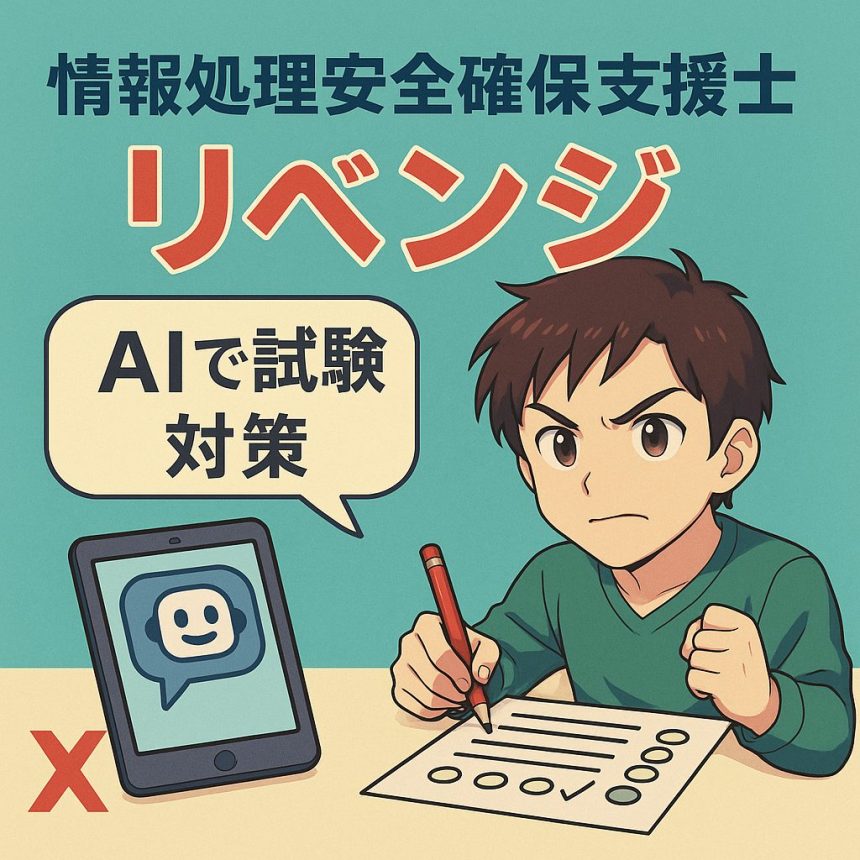※本記事の一部コンテンツ(文章・画像)はAIの支援を受けて作成しています。
令和7年度春期の情報処理安全確保支援士試験に落ちました。
正式な合格発表はまだですが、自己採点の結果、午前Ⅰで1点足りずに不合格。
午前Ⅱと午後問題は合格ラインを超えていただけに、悔しさが残ります。
再受験するにはやっぱり勉強時間も必要。
試験後にはAI関連技術の開発やPython,Rustの習得に勤しもうと思ってましたが、それらを犠牲にして試験勉強をするのかどうか悩みどころ。
悩んだ末に、試験勉強できるアプリをAI技術を使って作る!というところに落ち着きました。
悔しい…午前Ⅰであと1点届かず
この試験では、午前Ⅰを突破しないと午前Ⅱと午後の答案は採点すらされません。
セキュリティ系の設問は手応えがあったのに、セキュリティにあまり関係のない基礎知識が問われる午前Ⅰで足切り。
最後の「AIで生成された画像の著作権」みたいな設問、思わず「なんやねん、セキュリティ関係ないやん」とツッコみたくなりました(不正解でした)
原因は対策の甘さと過信
直近2回分の過去問をやって6割を超えていたので「いけるやろ」と思ってました。
実際は、半分はわかって、残りは消去法とか実務経験からの勘で正解してただけ。
今回はその“勘”がのきなみ外れたようです…。
午前Ⅰは過去問と酷似した出題が多いらしいので、もっと対策しておくべきでした。
セキュリティ知識ばかり深めて、基礎対策が疎かになっていたのは反省点です。
再受験はどうする?AIもRustもやりたいし…
現在は育休中で、インフラ関連の作業の依頼も受けています。
さらに、AI関連の技術やRustの学習も進めたい気持ちがあり、
「また試験に向けて時間を割くか?」というのが正直な悩みです。
育児休暇中で妻に「とるだけ育休なら働け」と厳しく言われているところ、
なかなか勉強時間も多くは取れません。
さける時間は、赤ちゃんが昼寝している間や、子供たちが寝静まり、片付けが終わった深夜など1日1~2時間程度でしょうか。
ChatGPTに聞いてみたら面白い提案が
迷いながら、とりあえずAI関連技術の学習を始めてみました。
その一環でChatGPTに「OpenAIのAPI使ってアプリ作りたいけど、どのようなアプリがおすすめですか?」と聞いてみました。
すると、「試験対策アプリを作ってみては?」という案が出て、ピンと閃きました。
落第した午前Ⅰの過去問をランダムで出力して勉強できるアプリケーションをAIを絡めて作ればよいのだ!
試験勉強 × アプリ開発 × AI活用
どうせやるなら、この3つを組み合わせて楽しくやったほうがいい。
試験対策アプリの構想メモ
- IPAで公開されている午前Ⅰの過去問からランダムに出題
- 回答後にChatGPTが解説を生成(必要に応じて)
- 解説内容は「選択肢の絞り方」や「用語の意味」など、選べると便利
- 過去問データや解説はDBに保存し、傾向分析にも活用
ChatGPTによる試験問題の解説は今回の試験勉強でも既に実践済みで、試験勉強には大いに役に立った(落ちたけど)アプリからOpenAIのAPIを呼ぶ形にしてChatGPTに解説してもらえば、それっぽく(AIを使った有用そうに見えるアプリケーションぽく)なりそう。生成AIではなく保存された固定文で返しているんじゃ?と思われるかも、という懸念もあり。
公開されている過去問はPDF形式。PDFにテキストではなく、画像が貼り付けられている。おそらく印刷された実際の問題用紙をスキャンしたものと思われる。テキストだったら簡単に抽出できるけど、画像上の文字は抽出できるのか?とChatGPTに聞いたらPythonで簡単にできます、とのこと。
問題文をPDFからアプリケーションで使える形に変換するのが大変そうと思ってました。その他疑問点含めて実現可能性を確認。問題なさそうなので作ってみることにしました。
作るアプリケーションは次の2つになるかと思います。
- 情報処理安全確保支援士の過去問(午前Ⅰ)をDBデータ化するアプリケーション
→これはどちらかというとアプリケーションに必要なデータを準備してくれるツール的なプログラム - ツールで作成したデータをもとにランダムに出題してくれるアプリケーション、AIによる解説付き。
→こちらが目的のAI関連のアプリ。
アプリ開発を始める前に考えたこと(補足)
何を作れば?どう進めれば?「何をどう決めればいいかわからない…」というのが最初の壁。
自分が実際に考えた流れやポイントを、参考までにまとめてみました。
まあ、自分はやりたいことをChatGPTに伝えて、アイデア出してもらいながら決めましたが(壁打ちとかいいますよね)
検討の流れ:ざっくりこんな感じ
- 目的の明確化:試験勉強の効率化、ChatGPTの活用体験
- 必要な機能:問題出題、解説生成、ジャンル分類
- 使う技術:Python(AI/OCR系に強い)、Google Colab、シンプルなWeb表示
よくあるつまずきと、その対策
| つまずきポイント | 対策例 |
|---|---|
| 何を作るか決められない | ChatGPTに相談してみる。アイデア出しは一人でやらなくていい。 |
| 技術選定で迷う | 情報が多くて学習コストの低いものから始める。完璧を目指さない。 |
| 作業が続かない/挫折しがち | ブログで進捗を公開する。軽いプレッシャーが継続の助けになる。 |
最初は「とにかく小さく試す」
- PDF1枚をOCRでテキストに変換してみる
- 1問だけChatGPTに解説させてみる
- 思いついた機能をプロンプトに投げて反応を見てみる
Pythonはまったく未経験ではないものの、いきなり規模のあるアプリケーションを作る自信もなく、小さな検証を繰り返しながら、少しずつ形にしていく予定です。
開発の進め方(ロードマップ)
- Google Colabで検証
- PDF→テキスト抽出(OCR)
- ChatGPT APIとの連携/プロンプト調整 - DB設計(問題文・選択肢・ジャンル・解説などの構造を考える)
- 本格開発へ
- フロントはシンプルなWeb表示
- バックエンドはPython(AI学習も兼ねる) - データ・コードをGitHubで公開
まとめ:落ちたことすら学びに変える
今回は悔しい結果になりましたが、ここで終わりにはしません。
落ちたからこそ、「じゃあどうする?」と自分に問い直す良い機会になりました。
勉強のためのアプリを作ることで、セキュリティもAIも、いっぺんに学べる。
何より「試験勉強が楽しくなる」ことを目指して、引き続き進めていきます。
次回は、実際のOCRの検証結果などをまとめて記事にしたいと思います。
ではまた!